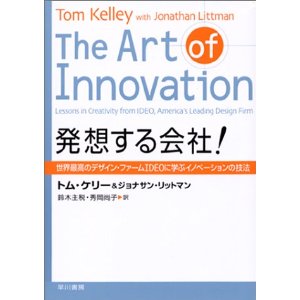年末年始に一時帰国し、結婚相手の家族に
はじめて会い、 タジタジしていました。 。。。
それでもやはり日本で食べる日本食は格別で、
至福のときを過ごしました。
この期間を使い多くの書籍を読みました。
普段なかなか日本語の読書が出来ず、
課題のケースやテキストブックの量に、
忙殺される毎日なので、貴重な時間でした。
伊賀 泰代氏の『採用基準』(ダイヤモンド社)も
読んだ書籍の一つでした。

その中で、「海外MBAへの企業派遣制度は
不毛な制度で、早めに廃止すべき」
と書かれています。
社費MBAという制度はよりより人材を獲得するための
マーケティングのツールとして使われており、
社費MBA派遣された人はまじめに授業を受けておらず、
いくつかのMBAコースからは社費派遣が煙たがられている、
と書いてありました。
これはいくつかの点で認識が違う部分があると思います。
1,MBAを意味のあるものにするかどうかは自分次第
以前にも書いたように、
MBAを意味のあるものにするかどうかは自分次第で、
それは社費派遣であろうが、私費であろうが一緒です。
MBAを卒業し、その価値を認められて良い転職をする人がいるならば、
社費派遣でMBAを卒業し、その価値や経験を
企業の経営へ活かすことができるはずです。
2,自分のまわりの社費派遣の友人はまじめに授業を受けている
ゴルフ三昧だったり、遊んでいてぜんぜん授業にでていない
という人もどこかにはいるのでしょうが、
私もまわりのクラスメートにそういう人はあまりいません。
逆に、どうやって面白い授業を取ろうか、
限られた時間をどうやって活用しようか、
と考えている人が大多数です。
3,社費派遣を優先して取るMBAスクールは結構ある
Global MBAもそうですが、
会社の選抜を勝ち抜いた実績を評価してくれる、
MBAコースがあります。
例えば、私自身十分な英語のスコアメイクができていないにもかかわらず、
いくつかの学校にインタビューに呼ばれたのは、
社内選抜を勝ち抜いた点も評価されたと思っています。
*****
一方、「MBAという修士号を持っている価値」という観点では、
アメリカと比べ、日本とアジア諸国では、
その価値が高く見られていないのも事実です。
例えば、MBAを持っているから転職に有利か、給与はUPするのか、
という点では、日本やアジアではあまり期待できないと聞きます。
(一部のコンサルティング会社や投資銀行を除きます)
アメリカでは、多くの場合が良い転職やよい給与に結びつくので、
アメリカ人以外の留学生がアメリカに残って就職活動をする、
高いモチベーションとなっています。
社費MBA派遣において最も重要なのは、
企業側が数千万に及ぶ投資を、
きちんと回収するつもりで、MBA派遣生を送りだしているのか、
というところだと思います。
派遣生の選び方や、その後のキャリアパスへのつなげ方が、
実はこの制度を意味のあるものにする上で重要であり、
十分に考慮する必要があると思います。
いろいろ考えることも多く、時間は少なくなってきました。
Winter Termも頑張っていきます。